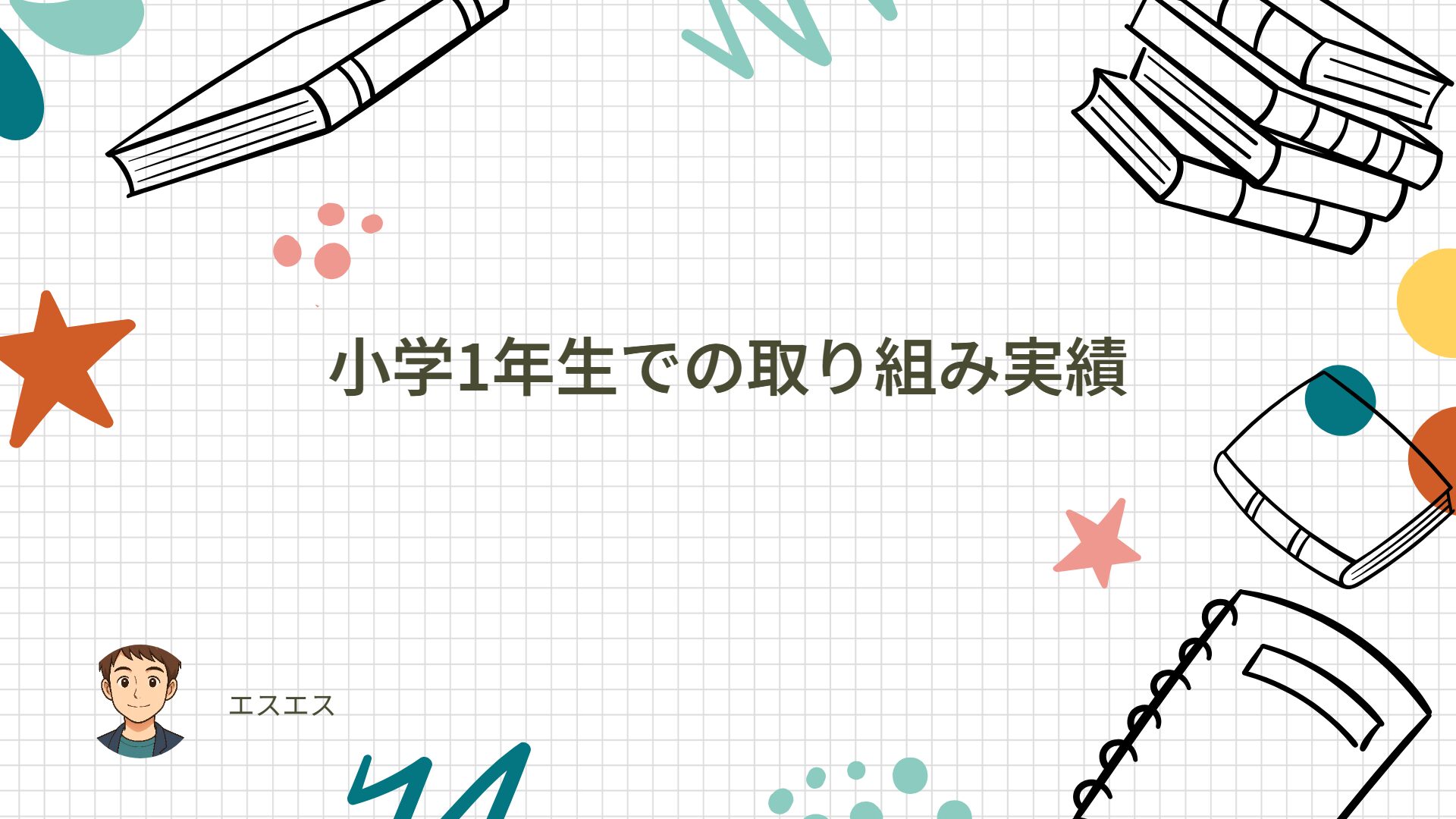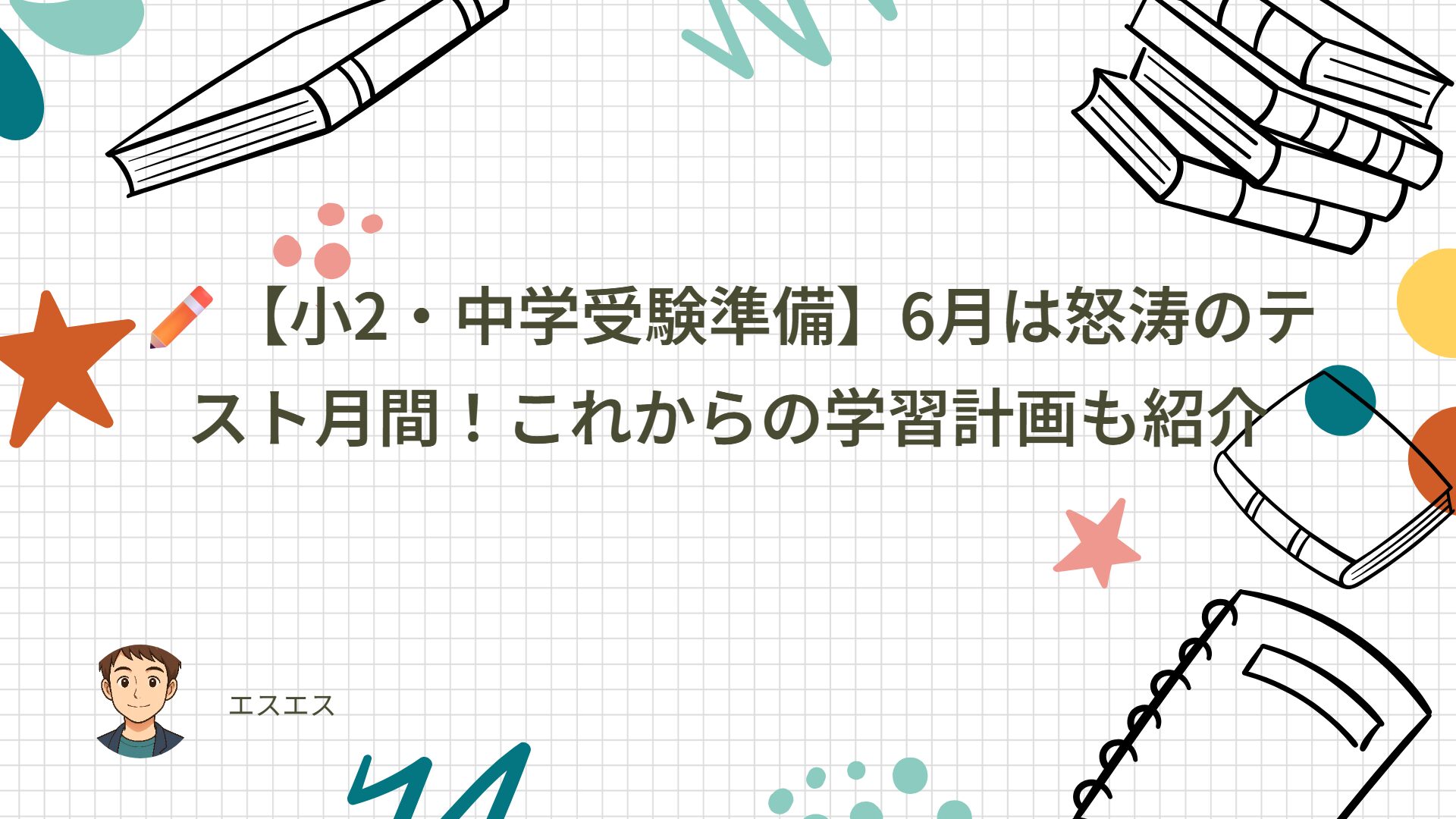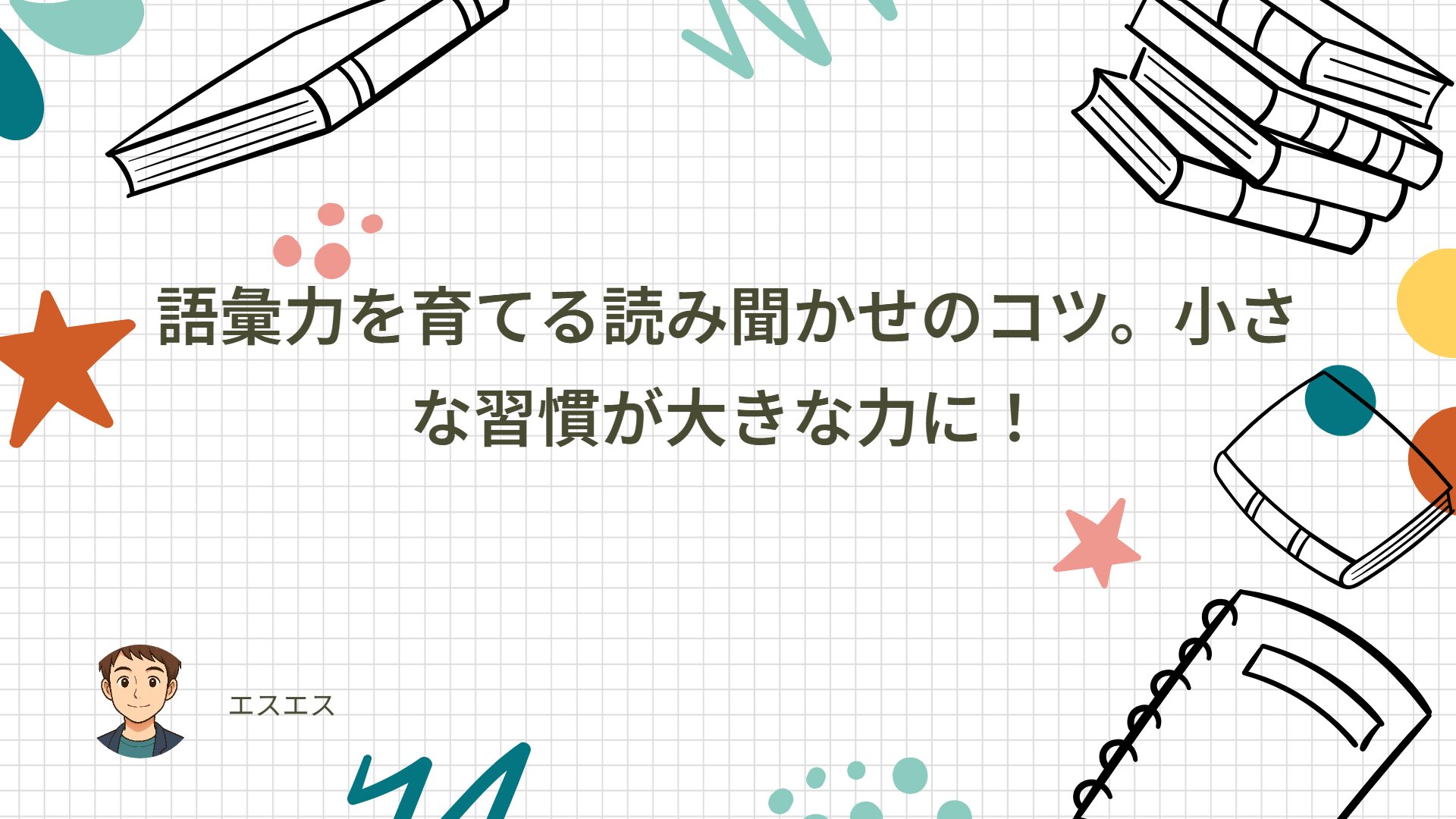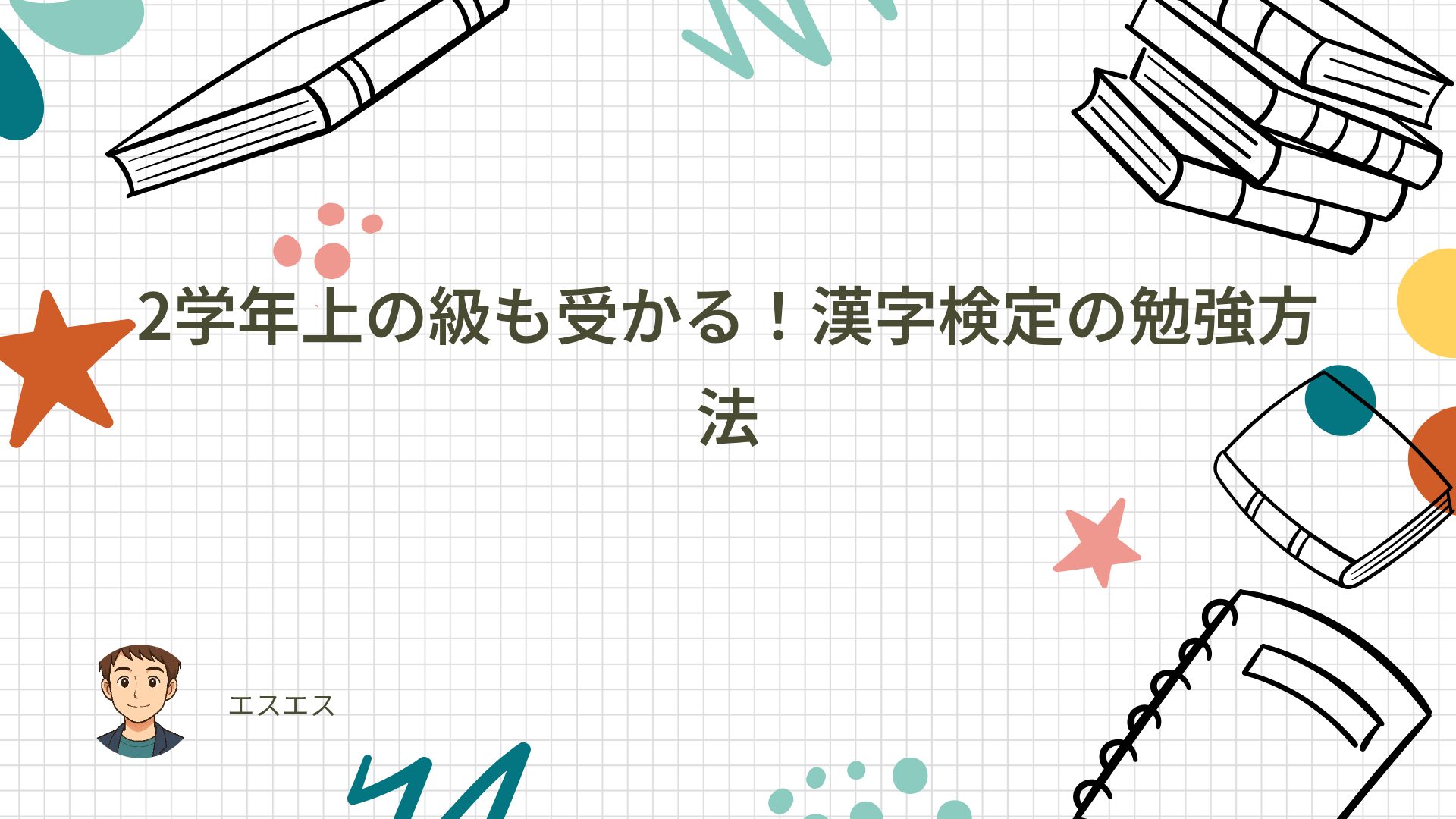身近なものを勉強に活かす
勉強はただテキストを進めるだけじゃなく、実生活の中でどのように使われているか目で見て手で触れながら学ぶ方がいい。
特に小学校低学年であればそういった体験が多いほどこれから学ぶことにつながって、思考力の礎となっていきます。
先日子どもと水のかさについて勉強しているときに、
L(リットル)、dL(デシリットル)、mL(ミリリットル)が新しい単位として出てきました。
これをテキスト通りに進めて、「単位覚えてね」だけで終わらせてしまうのは非常にもったいない。
こんな時こそ身の回りにあるものを活用しましょう。
試しに冷蔵庫の中を覗いてみると、
1000mLと表記された牛乳パックや500mLのペットボトルがあります。
実際に手に取って、1000mLがどのぐらいの量なのか体感させましょう。また500mLはその半分の量だということや1000mLは1Lと同じということも合わせて教えて体感してもらうとなお良しです。
こういった体験をさせつつ、これからの日常生活でLやmLの単位を使ったり実際に見させたりすると忘れにくい知識になり、思考力が育まれていきます。
更なる知識の定着へ、+αの知識や疑問に答えていく
テキスト通りに進めると大体この後に単位変換(1L=1000mL=10dL)などが出てきて終わりですが、+αの勉強をしていくとより強固な知識へと変わっていきます。
例えば、目の前にあった水槽に入る水は約40L、お風呂の水は約200Lなど直接書いてあるわけではありませんが、イメージできるものを使って教えていくのも大事です。
また、テキストや教科書にはdLが出てくるものの日常生活ではdLを使う機会がほとんどありません。
ではどんな時に使うのか一緒に調べたり、知っていることを教えてあげたりするのもおすすめです。
(ちなみにdLは野菜の種や医療機関でよく使われているそうです)